↑ トップ頁へ
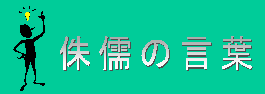
1999
|
↑ トップ頁へ |
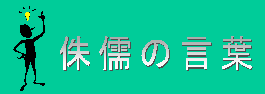
1999 |
|
|
|
学会少数派を守ろう…情報通信分野は、動きが激しく進歩も大きい技術領域である。当然活発な議論があって不思議ではない。にもかかわらず、日本の研究者は極めて慎重な発言に終始し、激烈な討論を避ける。技術の流れについて、独自の見解を声高に語る人は少ない。流れは大筋決まっており、多様な意見が発生しようもない、という見方もあろうが、本当だろうか。この分野では、技術は開発されると産業利用に直結する。このため、技術の採用決定に影響力ある人の意見に反する発言を極力避ける風潮があるのではないか。個々の研究者は、様々な意見を持っているにもかかわらず、そうした発言はほとんど伝わってこない。単なる杞憂であればよいが、筆者と同じ思いを抱く人もいたのであえて書く次第である。 この状態を心配しているのは、企業マネジメントよりは、最先端研究を進めている研究所のリーダー達である。発言を差し控えるだけならよいのだが、表立った議論を避けて来たために、現場の研究者は「技術の流れ」を読めないどころか問題意識まで喪失しているのではないかというのだ。確かに、先端技術に自ら挑戦しようという研究者は極めて少ないようだ。与えられたテーマをこなすという、受身型研究で満足する研究者が増えているというのである。 中堅の研究者のなかには、このままでは日本は後追い技術開発しかできなくなる、と指摘する人さえいる。学会レベルでの「思想統一」的な体質を改めないと、この流れは止めようは無いという見方もある。確かに、少数意見が正しいかどうかは、すぐには解らず、政策上からは、どうしても多数意見を尊重せざるを得まいが、多数派の見解が正当という根拠が薄弱のままで国家レベルでの技術の流れについて意思決定がなされている可能性も高い。健全な批判ができる少数派の存在は、科学の進歩にとって極めて重要なのだ。 教訓は数多い。デジタル放送技術の流れに関する議論の際、技術政策に疑問を感じながらも大勢に従った経験を持つ先端技術の研究者は少なくない。今ほどは深刻な問題と捉えていなかったのである。 ところが、インターネットの登場で、少数派の見方が危惧でなかったことが判明した。インターネット技術は突然登場したものではなく、日本でも、こうした技術が重要と早くから指摘した数人の研究者がいたという。しかし、技術の流れは大型交換機によるヒエラルキー型の頑強で安全な大規模通信システムの構築に向かった。結果は論評するべくもない。問題は、将来を見ぬく発言をしていた少数派の研究者はどう扱われたかである。ここでは、その動きを語るまい。実情を知る人達に、極めて高い問題意識があるのは当然だ。現在の体制のままなら、同じことが何度でも繰り返される可能性がある。 研究者は、単なるスローガンではなく、広い視野を確保するために実質的な動きをすべきだ。その第一歩は、少数意見を尊重し、耳を傾ける姿勢を貫くことではあるまいか。 侏儒の言葉の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2004 RandDManagement.com |