↑ トップ頁へ
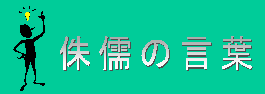
2000.1
|
↑ トップ頁へ |
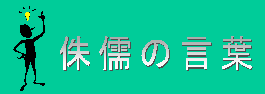
2000.1 |
|
|
|
インターネット電子レンジを何故支援しない…1999年に、ついにインターネット電子レンジが店頭に登場した。マスコミ情報では、売れ行き好調という。ところが、この製品に冷や水を浴びせるような意見もよく耳にする。「こんなもの何の役に立つのだ。」と言わんばかりの発言がなされている。確かに、役に立つのかと問われると答えにくいが、イノベーションの前触れかもしれない。電話機が登場した時、「こんなのものを使う人などいまい」と言われたことを、考えてみて欲しい。インターネット電子レンジは電話機ほどの新機軸商品とは言えないかも知れぬが、これからの時代を切り開くプロトタイプとは見なせよう。従って、こうした動きを起こした企業を応援する動きが欲しい。欠点の指摘ではなく、こうした新しい商品を育てようという建設的な意見に期待したい。そのような動きこそがインターネット時代の商品開発のあり方ではないか。 こうした先進的な製品に対して批判を浴びせる方々の観点が可笑しい訳ではない。「普通の消費者が何故このような複雑なものを必要とするのだ」という主張自体には反論しがたい。実際、店頭で販売員にインターネット電子レンジについて質問すると、不思議なやりとりになる。 「他とはどこが違うのですか?」 ---「通信で様々なレシピが見れます。」 「本では見れない特別なレシピがあるのですか?」 ---「そんなことはありません。しかし、本をとりに行かなくても、その場で見れます。」 「安い普及品に比べるとどの位の値段になります?」 ---「当店の一番安い商品と比べれば、3〜4倍の値段ですが、高機能商品と比べると倍まではいきません。」 「電話線を繋ぐとすぐに使えるのですか?」 ---「そうではありません。インターネットからの情報をアダプターに入れてお使い頂く仕組みです。」 「アダプターは付属品ですか?」 ---「別売品をご購入頂く必要があります。」 この会話で、素晴らしい製品と納得はしかねる。そもそも、料理の本を持って来る手間が大変だと思う人が、レシピの必要な料理を作る筈はなかろう。せいぜい、インターネット情報を見られる表示板をつけたもの位にしか見えまい。一見すれば、インターネットのオタク用商品とされかねない。 今迄なら、このような商品の場合、技術屋が顧客ニーズを考えずに興味本位か自己満足で作った製品と揶揄されるのが普通だった。消費者はメーカーが改良製品を出す迄待つしかなく、常に受身の動きしかできないのだから当然の批判だろう。しかし、インターネットの時代は違う。 インターネット接続型商品は、今のところ、普通の人にはすぐには使えない商品である。しかし、商品はこれから日々刻々変化していくのである。購入すれば終わりではなく、ソフトを更新することで自宅にある機器自体の機能も変化する。しかも、それは、メーカーの努力というより、ユーザー側の熱心な働きかけによる所が大きい。新しい使用方法に気付いたユーザーの知恵は、即座にインターネットを通して、その機器を利用する人全員に伝えることも可能になるからだ。消費者が製品開発過程に直接関与する時代が到来した訳だ。こうした通信型の商品が普及することで、一挙に我々のライフスタイルは変わる。今は、そのための産みの苦しみである。 実は、このようなインターネット接続型商品が普及すると、「産業革命」が勃発する。機器はすべて情報通信型になるので、色々な人が新しい利用方法を考え、それをまわりに教えるようになる。すると産業が急激に膨張する。といっても、市場が単に大きくなるのではなく、新機能や新サービスを通じて新産業に変貌することが特徴なのである。例えば、使い方が難しいとなれば、通信線で外部から直接手助けするサービスも生まれよう。機器の定期的遠隔故障診断事業への転進もありうる。要は、これまで以上にダイナミックな新事業の推進が可能になった。ここが、今までとは決定的に異なる。日本の研究開発に今求められているのは、こうした動きを支援する土壌をいかにつくりあげるかであろう。 先のインターネット電子レンジ自体は、現製品では、こうした流れに乗る製品とは言い難い面もある。しかし、この流れを加速させるか、旧型文化に留めるかは、この製品を支援するかどうかにかかっている。電子レンジでも、知恵ある人ならいくらでも利用方法の新アイデアはある筈だ。ボランティアで、新レシピを公開するのもよい。工夫した容器と特定のレンジ加熱条件で素晴らしい食べ物ができることを発見したなら、新しい事業を起こしてもよい。しかも、食品メーカーや料理研究家でもない、普通の主婦でも挑戦できる。こうして社会が変わり始めるのである。 メーカー側も、こうした新しい文化を生めるようなインターネット適合商品とインフラを出きる限り提供すべきだ。少なくとも、細かな応用ソフトをすべて自社で作る必要はない。できれば、消費者もソフト開発ができるように、出きる限り情報を公開し、文殊の知恵に期待すべきだ。そうすれば、ユーザーがブレークスルーを見つける可能性は高まる。素晴らしい消費者作成ソフトが生まれ、このソフトをよりうまく使えるようにメーカーが頑張り、機器もさらに進化する、という好循環を産みだしたいものだ。 侏儒の言葉の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2004 RandDManagement.com |