↑ トップ頁へ
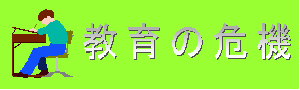
2007.8.27
|
↑ トップ頁へ |
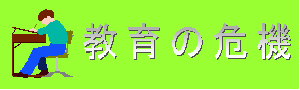
2007.8.27 |
|
|
|
Googleの20%ルールの意義…物理学会の“20%ルール”と3Mの“15%ルール”には、何の関連性もないという話をした。→ 「3Mの15%ルールの意義 」 (2007年8月23日)  これ以上に違うのが、Google の“20%ルール”である。
これ以上に違うのが、Google の“20%ルール”である。それは、Google がIT分野の企業であるからだ。化学産業とIT産業の違いを言いたいのではない。 IT分野では、すでに、1980年代、自由研究のマネジメントの難しさが知られていたからである。 1970年に編成された、Xeroxの中央研究所Palo Alto Research Center が技術的には“偉大な”「成果」をだしながら、ビジネスとしては、ほとんど実りを得られなかったのを皆が見てしまったからである。 なにせ、1970年代に、 “Smalltalk”、“Ethernet”、マウスの原型、レーザープリンタ等を生み出し、Macのグラフィカル・ユーザー・インターフェースの元ネタを提供したと言われているのである。(世界初のワークステーションと言われる“Alto”が開発されたのは、1973年のこと。(1)) もちろん、こうした先進技術は、その後、1981年に上市されたワークステーション“Star”として結実したと言えないこともないが、企業の収益に貢献したとは言い難い。 これらの技術を収益に結びつけたのは、ガレージから出発したAppleであり、町工場のようなSunだった。 自由な研究を行なう中央研究所不要論がでても当然だろう。 と言うのは、Xerox自体も、ベンチャー企業だからである。IBMが市場調査の結果、技術買収をことわったため自力でビジネスを立ち上げて大成功したのだが、大企業になって研究所を作っても、それによる見返りは余りにも小さかったからである。 要するに、身銭を切り、自分の一生を賭けてビジネス立ち上げに邁進しない限り、たいした事業にはならないと見る人が多かったということ。 それは、Google 自身の経験でもある。 誰も、技術の将来性を見抜けず、結局、自分達でビジネスと立ち上げたのだから。 そして、時代の寵児になった訳である。 そんな企業の“20%ルール”なのである。 つまり、従来型の自由研究とは質が違うということである。この施策のポイントは、心の底から突き動かされる“創造的な”仕事をせよと言うことだろう。 ましてや、「就職先を増やしたい。」などという物理学会の“20%ルール”とは似て非なるものと言ってよいだろう。 この方策は、Google にとっては生命線なのである。掛け声ではなく、これが、この組織の本質ということ。 2005年のForbes誌記事(2)を読めば、その内実の一端を感じることができよう。“Innovation is our bloodline. ”なのである 従って、Google の“20%ルール”とは、物理学会の記事ででてくるような、“社員のやる気を引き出し”などというものではない。(社員にやる気さえあればイノベーションが生まれると考えること自体がおかしいのだが.) 「好きな研究をして、人間としての幅をつくれば、もっと大きな仕事ができる」などという話など通用する筈もない。 そもそも、この企業、創造性が発揮できそうなピカ一人材を世界から集めたのである。そのための、リクルートには徹底的に力を入れた。言うまでもないが、日本の大学からの引き抜きも含まれる。 日本企業のように、修士何名、博士何名、採用予定などというものではない。 当然ながら、自分の能力を信じている人達は、こぞってGoogle入社を熱望した。雇用条件の良さもさることながら、Google側も、その意義を伝えた。(3)お陰で、ラボで切磋琢磨しながら、頭脳の世界一を目指したい人がこぞって応募したということ。このため熾烈な入社競争が繰り広げられたのである。 どんな状態かは次の一文でわかろう。 “Some applicants may start with one of Google's famous--and ridiculously difficult--exams.” 繰り返すが、本気で、イノベーション創出に賭けているのである。・・・“Companywide a full 10% of time is spent dreaming up blue-sky projects. ” Googleでは、プロジェクトを牽引するのは、ピカ一人材であり、こうした人材をどうやって組織的に活用して、成果に結びつけるか、が問われているということ。 要するに、創造性あるピカ一人材が互いに知的な刺激を与え合い、切磋琢磨するような環境をつくるためにどうするかを考え抜いた結果の一つが“20%ルール”ということでしかない。ここだけにハイライトを当てるべきではないのである。 おわかりだと思うが、“20%ルール”だけ真似をしたところで、何の意味もない。 そもそも、どのようにしてピカ一人材だと判定するかの能力も無いのが普通の企業である。博士採用にしても、どんな人なら貢献してくれそうかも、はっきりさせることが必要だろう。 Googleに限らず、いわゆるAptitude Testで人材評価するなど、方法論を持たないのでは話になるまい。 結局のところ、“よくわからないが、あの人は視野が狭そうだから、採用は止めておこう”ということになる。 逆に言えば、“あの先生がお勧めしているから、採用しておくか”といういい加減な判定が行われる。その結果はたいてい悪いから、常に採用を躊躇することになるだけのことだ。 現代の技術マネジメントは、知恵を組織的に生み出す施策に焦点が当てられているのである。 それは、当然のことながら、企業文化に大きく依存する。企業文化に合わない人は無用といっても過言ではない。 つまり、企業は、当社として必要な研究者としての人材像を示す必要があるということ。それに合わせたリクルートになるわけだ。 企業のラボも、決して創造性ある専門人材だけに依拠している訳ではない。高度な実験のプロや、セネラリストも不可欠である。そんな人達のチームをどう作るかのノウハウで勝負がつくということ。 人々の知恵をどう組織力に転化できるかのマネジメント競争が行われている訳である。 この流れに乗らない施策は、たとえプラス効果が見込めても、長期的にはマイナス効果につながる可能性が高いということ。 物まねの“20%ルール”導入など最悪と思って間違いない。 “Getting the most out of knowledge workers will be the key to business success for the next quarter century.”(4)なのだ。 --- 参照 --- (1) 年表と日本の歴史的コンピュータ http://www.ipsj.or.jp/katsudou/museum/history/history_ws.html (2) Quentin Hardy: “Google Thinks Small” Forbes [2005.11.14] http://members.forbes.com/global/2005/1114/054A.html (3) “Top 10 Reasons to Work at Google” http://www.google.com/support/jobs/bin/static.py?page=about.html&about=top10 (4) Eric Schmidt(CEO) & Hal Varian: “Google: Ten Golden Rules” Newsweek [2005.12.2] http://www.msnbc.msn.com/id/10296177/site/newsweek/ 教育の危機の目次へ>>> トップ頁へ>>> |
|
|
(C) 1999-2007 RandDManagement.com |